【第4回】国際的な概念化の潮流——米国を中心とした取り組み
こんにちは!r-youngです😋
第4回は、
「高度実践看護の概念化」に関する国際的な動き
を紹介します。
特に米国での取り組みを中心に、
どのように共通理解が築かれ、制度として整備されてきたのかを見ていきましょう!
◆ なぜ国際的な視点が必要なの?
高度実践看護の役割や教育は国によって大きく異なります。
でもその違いの中にも、共通する課題があるんです!
それは…
- APRNsの役割や実践範囲の明確化
- 教育プログラムと認証制度の整合性
- 多職種連携や政策提言への対応
こうした共通課題にどう取り組んでいるかを見ることで、
私たちの足元(日本)を見直すヒントにもなります!
◆ 米国:概念化の先頭を走る国!
◎ Affordable Care Act(ACA:2010年)
→ 医療の質向上とコスト削減のために、APRNsの活用が明確に推進されました!
◎ The Future of Nursing(2011年)
→ APRNsが「最大限の教育と訓練に応じた実践」を行えるよう求めています。
◎ コンセンサスモデル(APRN Joint Dialogue Group, 2008)
→ 「APRNsとは誰か?」を共通言語で定義した画期的な枠組み!
このモデルについては、次回たっぷり解説しますのでお楽しみに!
◆ APRNsを取り巻く制度的な整備も進んでる!
◎ DNP(Doctor of Nursing Practice)プログラムの拡充
→ 臨床力と理論力を統合する教育モデルが確立!
◎ IPEC(Interprofessional Education Collaborative)などによる専門職種間教育
→ 看護・医学・薬学などの大学院生が一緒に学び、役割理解を深めています!
◆ カナダ、オーストラリア、シンガポールでも進む動き
◎ カナダ看護協会(CAN)
→ 「高度看護実践」という言葉を用い、APRNの役割を法的に明確化しています!
◎ オーストラリア
→ CNSやNPの役割を区別するため、実践モデルや研究が行われています。
◎ シンガポール
→ 大学医学部がAPRNsを養成する教育プログラムを整備(National University of Singapore など)
◆ 共通するのは「概念化」の必要性!
どの国も、
「高度実践看護を制度として定着させるには、明確な定義と共通言語が不可欠」
という点で一致しています。
そのために、各国で
- モデルの開発
- 教育カリキュラムの整備
- APRNsの実践範囲の明文化
- 他職種との連携の推進
が行われているのです!
◆ 課題もあるけど、希望もある!
とはいえ…
- 各国で用語や定義がバラバラだったり
- 「高度実践」と「高度看護実践」が混在していたり
- APRNsと他職種の区別が不明瞭だったり…
まだまだ課題は山積みです。
でも!
その課題に真剣に向き合い、対話しながら整備している姿勢こそ、私たちが学ぶべき点なんです!
◆ まとめ:第4回のポイント
・米国を中心に、高度実践看護の制度化と共通理解の動きが進んでいる!
・ACA、コンセンサスモデルが改革を後押し!
・カナダやシンガポールなど他国も法整備や教育体制を整備中!
・共通するのは、「定義」と「枠組み」を明確にすることの重要性!
次回(第5回)は、いよいよ登場!
「APRNコンセンサスモデルの構成と意義」
を詳しく解説します!
お楽しみに!

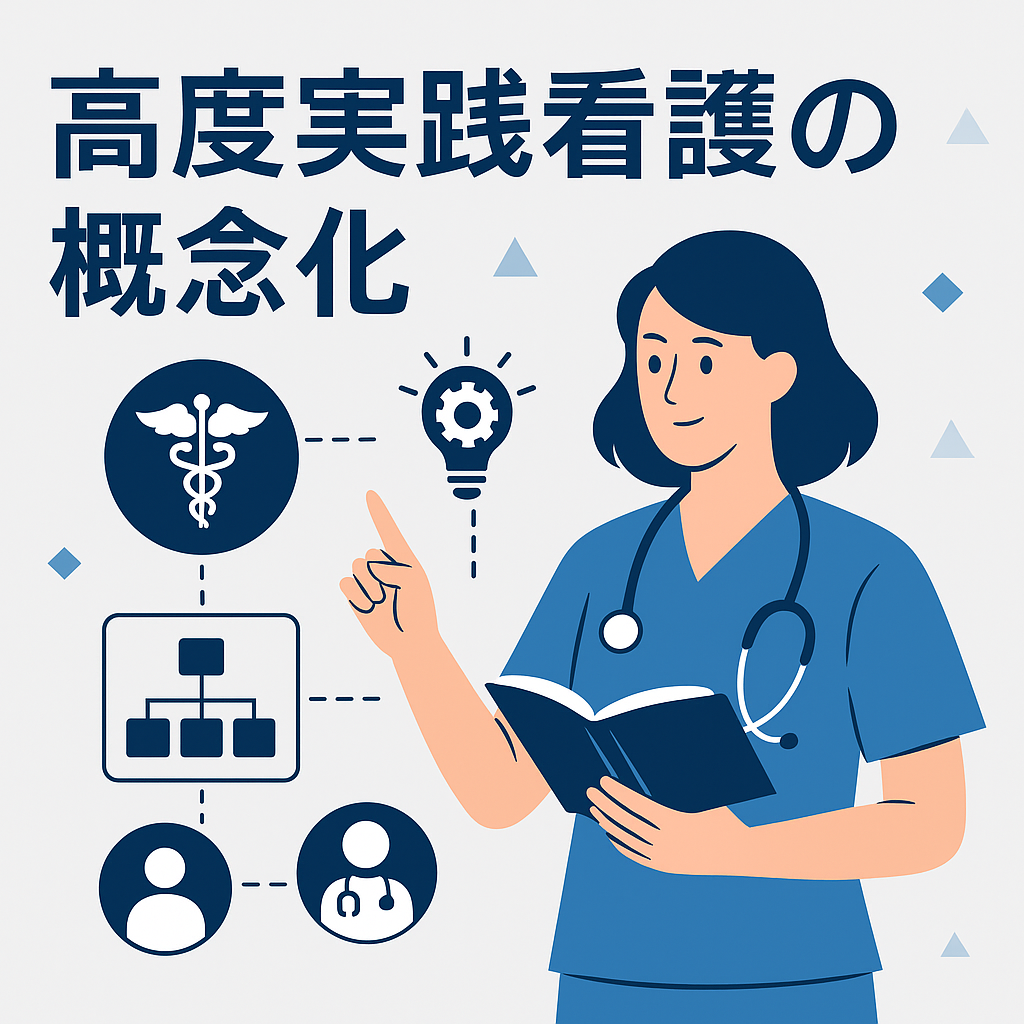

コメント