第6回:1980年代〜処方権とNPの戦い!現場から法廷まで…!?〜
1970年代に教育が広がったNP。
次のステージは
“実践の権利”
をめぐる本格的な戦いの時代に突入します。
処方していいの?
診断ってどこまで?
この頃、現場だけじゃなくて、
法廷や国の制度の場面でもNPの存在が問われるようになっていきます。
新しいNPがどんどん誕生!
1980年代は、
専門領域NPの登場ラッシュ!
ファミリーNPに加えて…
- 救急NP
- 新生児NP
- 急性期NP(ACNP)
など、さまざまな分野でNPが活躍するようになりました。
中には三次救急やICUで働くNPも登場し、
もう「院外だけの活動じゃない」時代に突入していきます。
処方権をめぐるバトル勃発
NPの大きな壁のひとつが
「処方権」でした。
当時はまだ、規制薬物を処方するにはDEA(麻薬取締局)の登録番号が必要。
でも、これって医師とか歯科医しか取れなかったんです…。
NPたちは
「ちゃんと教育を受けて、実践してるのに、なぜ処方できないの?」
と不満を募らせていきます。
法廷での勝利「Sermchief v. Gonzales」
1983年
ミズーリ州で起きた有名な裁判が
2人の女性NPが「無免許で医療行為をした」として訴えられたのですが…
なんと、州の最高裁判所でNP側に軍配!
「APNの実践は、法定の制限がなくても進化できる」と認めたんです✨
これは、NPという職種が法的に一歩前進した瞬間でもありました。
DEA登録と「Mid-Level Provider」制度の誕生
1990年代に入る直前、DEAは
「Mid-Level Provider」
(中間職プロバイダー)
という新しいカテゴリを作って、
NPにも処方番号を発行することを認めるようになります。
Mid-Level Providerという名称に関する解説はこちら。
(※最近ではこの呼称については否定的な意見が多いようです。)
これによって、州で処方権を認められていれば、NPでも麻薬系の薬が処方可能に!
まさに、NPにとっては大きな進展でした!
今日のまとめ
- 1980年代は専門NPが増え、フィールドが広がっていった
- 処方権をめぐる制度的な壁が大きな課題に
- 裁判所の判例やDEAの制度改正で、NPの実践は一歩ずつ前進
- 「診るだけじゃなく、処方まで」の道が開き始めた時代!
次回は、新生児や急性期NPの誕生にフォーカス。
ハイリスク患者のケアまで担うNPたちの、専門職としての進化を追っていきます。
ではまた!👋

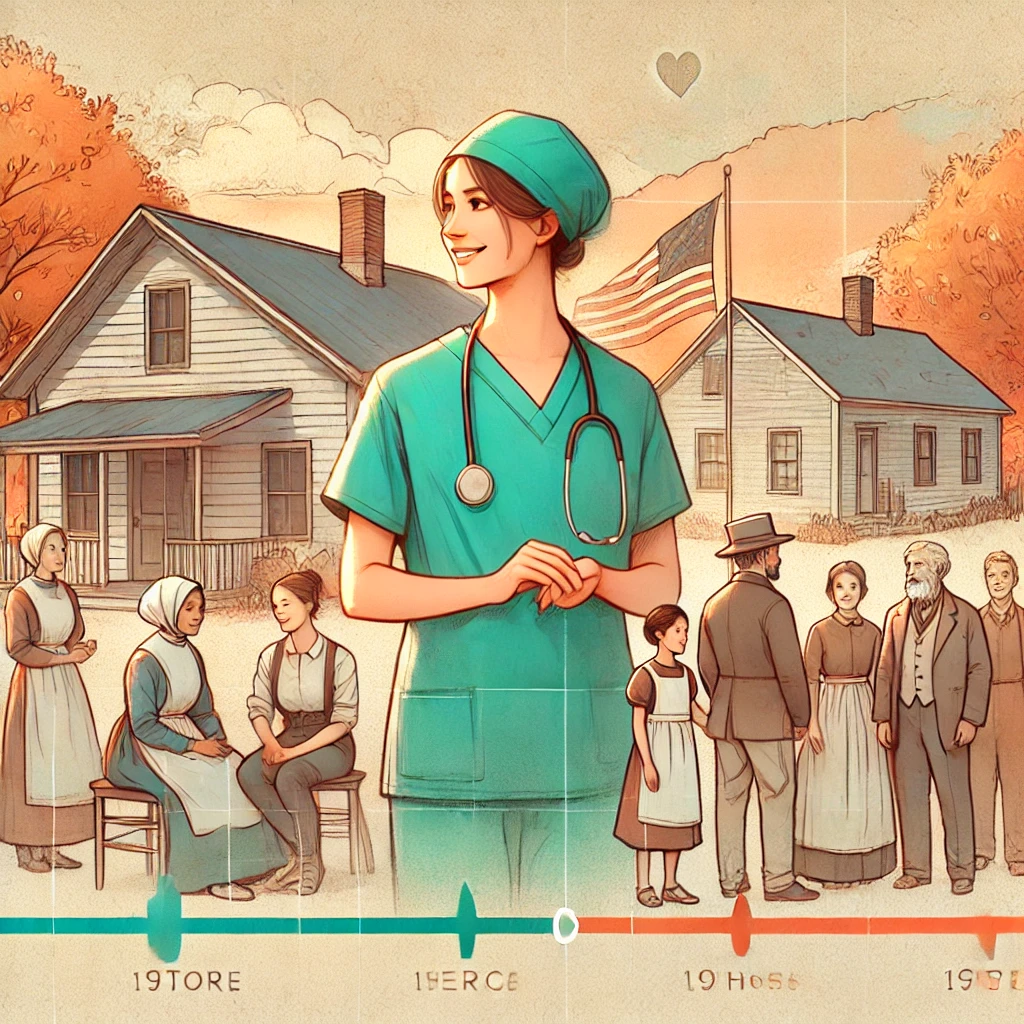
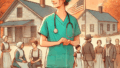
コメント