第5回:1970年代の広がりと葛藤〜NP教育の拡大と揺れる専門職のアイデンティティ〜
1960年代後半にスタートしたNP制度は、たちまち全国的な関心を集め、1970年代には教育プログラムが急増していきます。
同時に、NPという新しい専門職のアイデンティティや役割を巡る議論も白熱していきました。
全米に広がるNP教育プログラム
コロラド大学で始まったNPプログラムの成果を受けて、多くの大学が類似のプログラムを立ち上げました。
特に注目されたのは、
小児NP(PNP)からファミリーNP(FNP)への拡張です。
この時期は、認定プログラム中心で、修士号を必要としないコースが多く存在していました。
医学モデル vs. 看護モデル
急速な普及の中で、
「NPは医学モデルに近すぎるのでは?」
という懸念も看護界から上がり始めます。
診断や処方を行うNPの役割に対して、
看護独自の価値観との折り合いが問われたのです。
特に看護理論家のマーサ・ロジャースは
「NPは医師の代わりをする存在ではない」として強く反対しました。
このような批判は、NPという職種のあり方をめぐる職能内の葛藤として続いていきます。
教育の標準化に向けた動き
1974年、NP教育者たちはノースカロライナ州チャペルヒルで初の全国会議を開催。
これが後の
(National Organization of Nurse Practitioner Faculties)
の設立につながり、NP教育の質の保証と標準化の第一歩となりました。
また、州レベルでの法整備も始まり、RNの役割拡大を法的に認める流れも出てきました。
政策的サポートと評価研究の導入
連邦政府もNPの役割に注目し、保健教育福祉省(HEW)は拡大するNPの役割を評価する委員会を設立。
NPの実践が、医療アクセスの平等化やコスト削減に有効であるという調査結果が得られ、公的支援が進む契機となりました。
今日のまとめ
- 1970年代はNP教育が全米に拡大し、多様な役割が登場
- 看護界内では「医学化」に対する反発もあり、専門性の揺らぎが議論に
- NONPF設立など、教育の質と一貫性を確保する取り組みが始まる
- 政策的支援により、NPは制度としての基盤を整えつつあった
次回は1980年代。
NPの数がさらに増加し、処方権や法的地位を巡る専門職種間の対立と裁判闘争が本格化していきます。
ではまた!👋

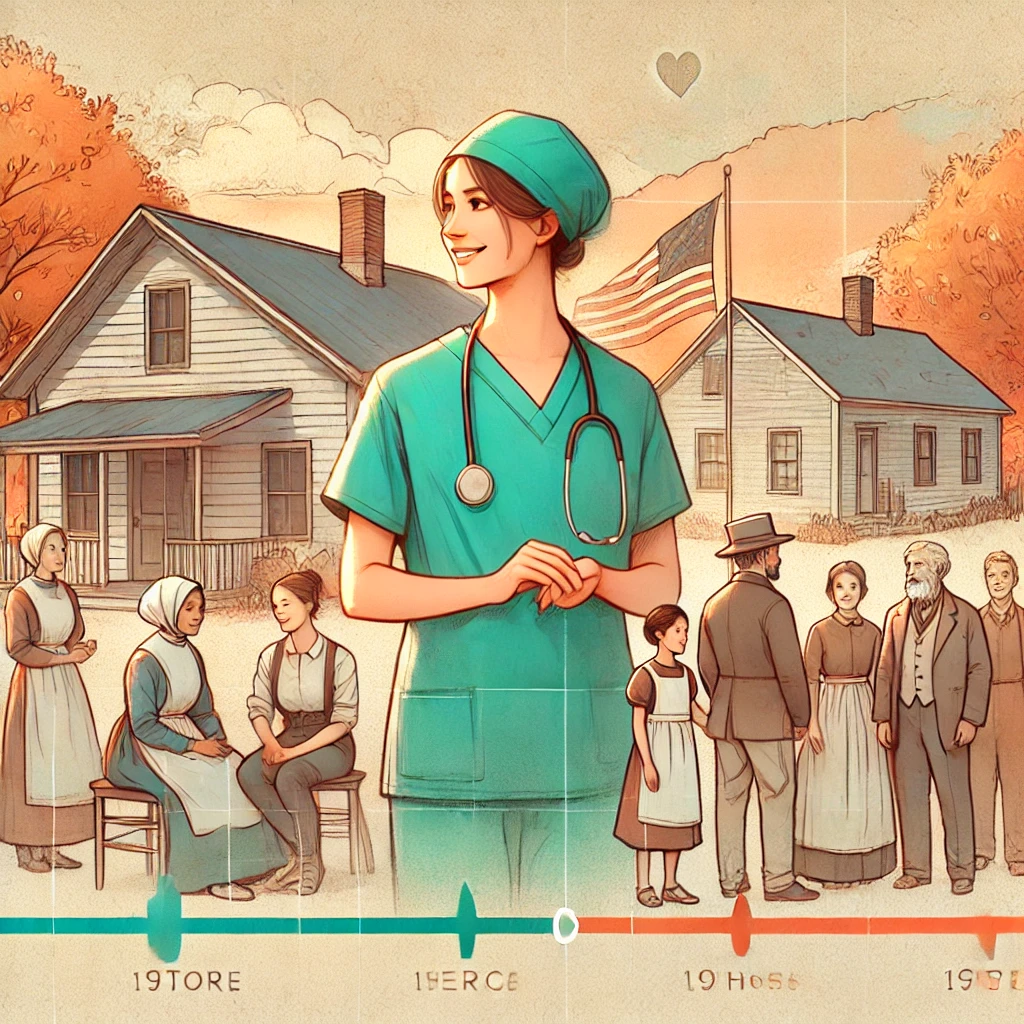
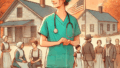
コメント