【第1回】高度実践看護とは何か?——その定義と共通理解の重要性
みなさん、こんにちは!
r-youngです!😁
ゴールデンウィークで心も体もリフレッシュできていますか?
私は特に予定もなく、通常運転🚙
この時期はどこに行っても混雑しているので、仕事している方が良いですね!
さて、
今日からスタートするこのシリーズ、
診療看護師(NP)やCNSを含む高度実践看護師(APRN)の実践を、
理論とモデルの視点からじっくり解説していきます。
日本はこの視点が諸外国と比較して大きく遅れていると言わざるを得ない、そう考えています。
初回となる今回は、
「高度実践看護(Advanced Practice Nursing)ってそもそも何なの?」
という基本のキからスタートします!
◆ 高度実践看護ってどういうこと?
「高度実践看護(APN)」
この言葉、最近よく耳にするようになりましたよね?
でも、実際のところ
「高度ってなに?」
「普通の看護とどう違うの?」と感じる方も多いはず。
文献では、APRN
(Advanced Practice Registered Nurse)は、
患者や家族の健康改善、疾患への対処、尊厳ある死の支援といった目的のために、概念・モデル・理論を活用しながら実践を展開している
とされています。
それだけでなく、
・臨床ケアの説明
・介入の計画
・アウトカムの評価
・対人関係の構築
などにも、
この「高度実践看護の枠組み」が重要な役割を果たしているんです。
◆ なぜ「概念化」が必要なの?
さて、ここでキーワードになるのが
「概念化」という言葉。
「えっ、概念とか理論って現場のナースに必要なの?」
と疑問に思う方もいるかもしれませんが……
これが、とても大事!
すべてのAPRNs(NP、CNSなど)は、
経験年数に関係なく、共通のプロセスと用語に依存してケアについてコミュニケーションを図っています。
つまり、共通言語があるからこそ、チームで一貫したケアが提供できるというわけ。
そのためには、
APRNsが使う理論やモデル、用語についてみんなで共通理解をもつことが必要不可欠なんです。
◆ 高度実践看護の「枠組み」がなければ…
もし高度実践看護に明確な枠組みがなければどうなるかというと…
・NPと医師、CNSの役割がごちゃごちゃになる
・教育も認証もバラバラになり、現場での応用が難しくなる
・多職種との連携もうまくいかず、ケアの質が下がる
…というように、せっかくの高度な実践もチグハグになってしまうリスクがあります。
だからこそ、あいまいな言葉をしっかり定義し、「高度実践ってこういうこと!」と説明できるようにしておくことが、今まさに求められているんですね。
◆ 世界の動きも踏まえた「共通理解」の重要性
この考え方は、アメリカだけでなく世界中で共通しています。
たとえば米国では、
「Affordable Care Act(ACA)」や
「Future of Nursing」報告書
によって、APRNの役割や教育に大きな改革が行われました。
他にも、
カナダやシンガポール、
中国本土などでも、
APRNの定義や教育の整備が進められており、「高度実践看護とは何か?」をはっきりさせる動きが世界中で起こっているんです。
◆ 看護職全体が押さえておくべき基礎
この「高度実践看護の概念化」は、
NPやCNSといったAPRNsだけのものではありません。
むしろ、
一緒に働くスタッフナースや他職種が共通理解を持ってこそ、チームとしての力が最大限に発揮されるものです。
その意味で、概念やモデル、共通言語の整備は、看護職全体の未来をつくる基盤ともいえるでしょう。
◆ まとめ:第1回のポイント
・高度実践看護は、理論やモデルをもとに、臨床・教育・政策をつなぐ架け橋!
・「概念化」はチーム医療の共通言語づくりの第一歩
・世界中でAPRNsの定義と実践が明確化されている
・共通理解が、質の高い看護とチームケアを支える!
次回(第2回)は、
「概念モデルとは何か?——高度実践看護を理解する枠組み」について解説します!
お楽しみに〜!

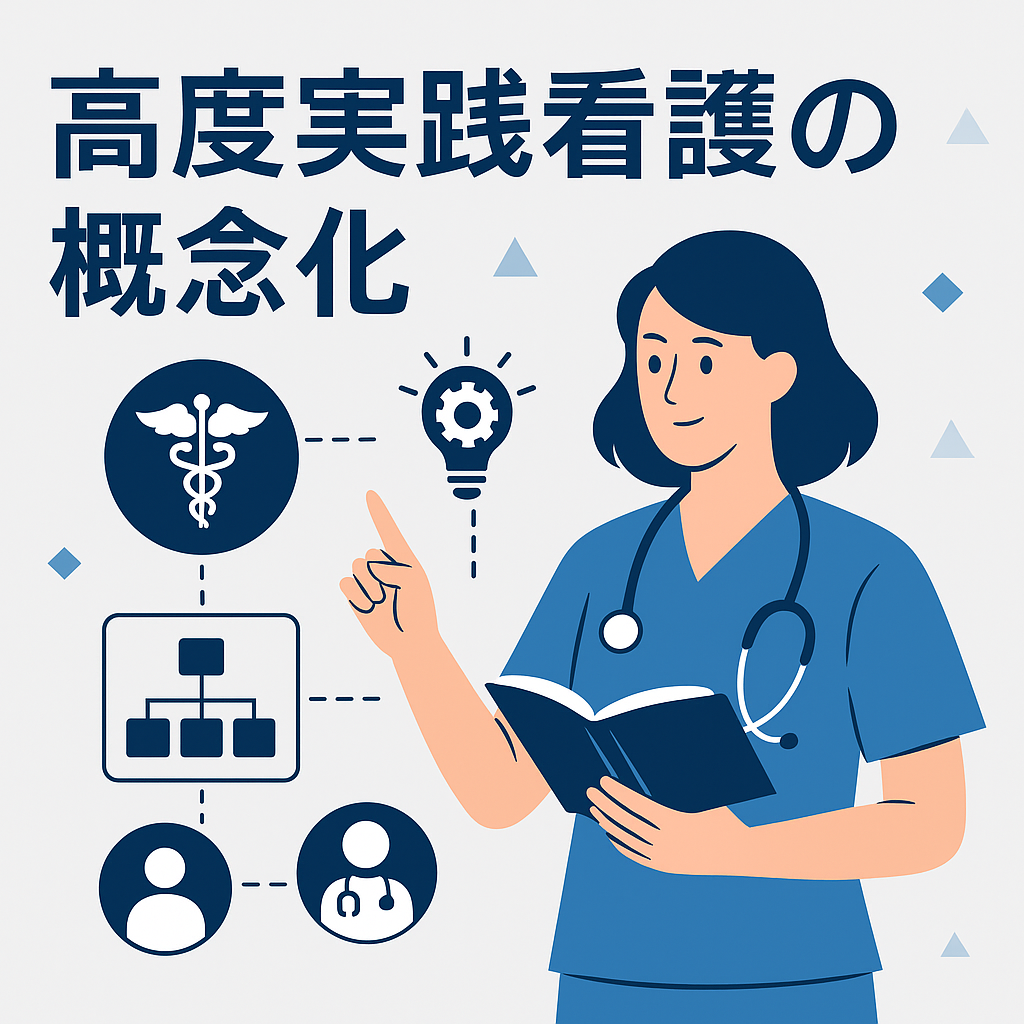
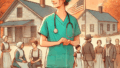

コメント